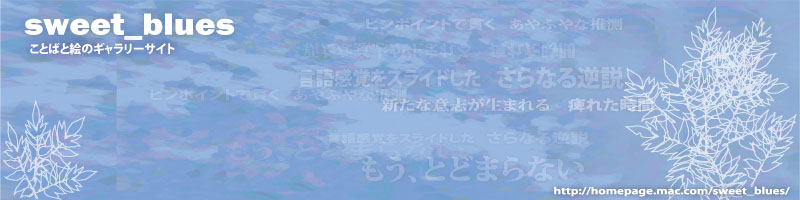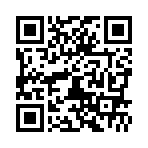スポンサーサイト
それを「希望」と名づけよう
2011年03月26日
長いことブログを休止してしまいました。
その間、東北関東大震災がありました。
日本中が身も心も打ちひしがれ、不安と恐怖に苛まれる日々が続いています。
被災された方には、心からお見舞い申し上げます。
また亡くなられた方のご冥福をお祈りも申し上げます。
さて、震災直後の3月13日、佐野元春さんが誕生日に寄せて次の詩を発表しました。
タイトルは、『それを「希望」と名づけよう』
http://www.moto.co.jp/
この詩に関して、元春ファンの間でも賛否両論が交わされました。
また、1988年に発表された「警告どおり計画どおり」という曲が、本人の意図とは別な意図で使用され、これも物議を醸しました。
http://www.kasi-time.com/item-15652.html
詩は乱暴な言い方をすれば「比喩」であり、いくとおりもの捉え方ができます。
だから、メッセージ性の強い作品は、後々の時代になっても生き続け、思いもしない評価を受けることもあります。
難しいな、としか言えないんですが・・・。
by shu
その間、東北関東大震災がありました。
日本中が身も心も打ちひしがれ、不安と恐怖に苛まれる日々が続いています。
被災された方には、心からお見舞い申し上げます。
また亡くなられた方のご冥福をお祈りも申し上げます。
さて、震災直後の3月13日、佐野元春さんが誕生日に寄せて次の詩を発表しました。
タイトルは、『それを「希望」と名づけよう』
http://www.moto.co.jp/
この詩に関して、元春ファンの間でも賛否両論が交わされました。
また、1988年に発表された「警告どおり計画どおり」という曲が、本人の意図とは別な意図で使用され、これも物議を醸しました。
http://www.kasi-time.com/item-15652.html
詩は乱暴な言い方をすれば「比喩」であり、いくとおりもの捉え方ができます。
だから、メッセージ性の強い作品は、後々の時代になっても生き続け、思いもしない評価を受けることもあります。
難しいな、としか言えないんですが・・・。
by shu
love trinita! love football!
2011年03月07日
浅春の風が、また、あの狂躁を運んでくる
ざわめく心、抑え切れず
熱に浮かされたいいオトナたちが
たったひとつのボールの行方に右往左往する
フットボール・ジャンキーにつけるクスリはない
スタジアムは麻薬だ
ピッチに繰り広げられる流麗なアートに
肉体の限界を超えボールを追う健脚に
魂と汗と堅牢な体のぶつかり合いに
跳び、歌い、叫び、こだまするチャント、ひるがえるフラッグ
スタンドから見つめる目
歓喜と溜息の紙一重
たった一度のチャンス
このチャンスを逃せば、もうベンチ入りはない
体を縛り付ける緊張感、あせり
縮こまった体は、あと半歩が伸びきらない
ボランチの芸術的なサイドチェンジのキックは
ディフェンスの裏へやさしい弧を描く
ここを抜けきれ
足を伸ばせ
すがるディフェンダーを振り切り
闇雲にペナルティエリアへ突入する
見えた
ゴールキーパーとポストのわずかなすきま
縮こまった足を一閃、振り抜く
オー、オー、オー、オー、
ゲットゴーール、ゲットゴーール
浅春の風に乗って
遠く遠く青空の彼方へ
スタジアムの熱狂は舞い上がる
we love trinita! we love football

by shu
ざわめく心、抑え切れず
熱に浮かされたいいオトナたちが
たったひとつのボールの行方に右往左往する
フットボール・ジャンキーにつけるクスリはない
スタジアムは麻薬だ
ピッチに繰り広げられる流麗なアートに
肉体の限界を超えボールを追う健脚に
魂と汗と堅牢な体のぶつかり合いに
跳び、歌い、叫び、こだまするチャント、ひるがえるフラッグ
スタンドから見つめる目
歓喜と溜息の紙一重
たった一度のチャンス
このチャンスを逃せば、もうベンチ入りはない
体を縛り付ける緊張感、あせり
縮こまった体は、あと半歩が伸びきらない
ボランチの芸術的なサイドチェンジのキックは
ディフェンスの裏へやさしい弧を描く
ここを抜けきれ
足を伸ばせ
すがるディフェンダーを振り切り
闇雲にペナルティエリアへ突入する
見えた
ゴールキーパーとポストのわずかなすきま
縮こまった足を一閃、振り抜く
オー、オー、オー、オー、
ゲットゴーール、ゲットゴーール
浅春の風に乗って
遠く遠く青空の彼方へ
スタジアムの熱狂は舞い上がる
we love trinita! we love football

by shu
海炭市叙景
2011年03月03日
日々の暮らしに疲れ、よどみ、すり減っていくうちに、たいせつなものを失っていく人々が主人公。
そしてまた、そんな人々がすれ違いながら生活を紡いでいる"海炭市"そのものも主人公だといえる。
景気も悪く、人間関係も狭く膠着し、およそ暮らしていくには快適とは言いがたい地方都市。
でも、ここに出てくる人々は、決して海炭市から出て行こうなどとは思ってはいない。あるいは、そういう発想がないのか。
いろんな不満を抱えながらも、海炭市に執着し、ある種の諦観をもって、そこで生きていこうとしている。
それは、ただたんに郷土愛などというストレートなものではないと思う。
愛も憎しみも様々な感情を孕んだ故郷への思い。
かつて確かにあった居場所に帰りたいという幻想。
身動きの取れない疲弊した現実。
それらが彼らを執拗に”海炭市”に引き止めているのではないだろうか。
だから物語は悲しい。
しかし、どこかに救いがあるようにも思える。
5つの物語が、シンクロし、かすかに交わり、すれ違っていくさまは、とても美しく描かれる。
戻りたい場所は"海炭市"にある。
けれど、決して戻れない。
多かれ少なかれ、誰にも思い当たる物語かもしれない。
余談だが、「海炭市叙景」というタイトルの字面と音の響きがとてもよい。
こういうのも映画の重要なファクターだと思う。
by shu

そしてまた、そんな人々がすれ違いながら生活を紡いでいる"海炭市"そのものも主人公だといえる。
景気も悪く、人間関係も狭く膠着し、およそ暮らしていくには快適とは言いがたい地方都市。
でも、ここに出てくる人々は、決して海炭市から出て行こうなどとは思ってはいない。あるいは、そういう発想がないのか。
いろんな不満を抱えながらも、海炭市に執着し、ある種の諦観をもって、そこで生きていこうとしている。
それは、ただたんに郷土愛などというストレートなものではないと思う。
愛も憎しみも様々な感情を孕んだ故郷への思い。
かつて確かにあった居場所に帰りたいという幻想。
身動きの取れない疲弊した現実。
それらが彼らを執拗に”海炭市”に引き止めているのではないだろうか。
だから物語は悲しい。
しかし、どこかに救いがあるようにも思える。
5つの物語が、シンクロし、かすかに交わり、すれ違っていくさまは、とても美しく描かれる。
戻りたい場所は"海炭市"にある。
けれど、決して戻れない。
多かれ少なかれ、誰にも思い当たる物語かもしれない。
余談だが、「海炭市叙景」というタイトルの字面と音の響きがとてもよい。
こういうのも映画の重要なファクターだと思う。
by shu